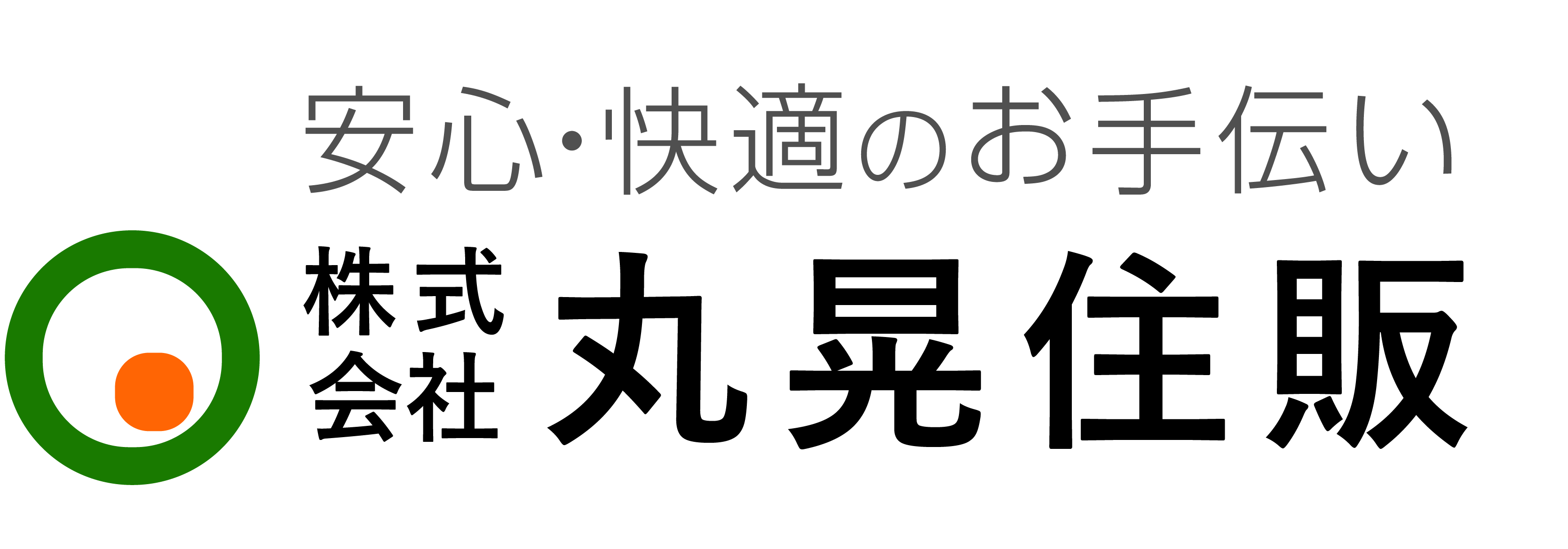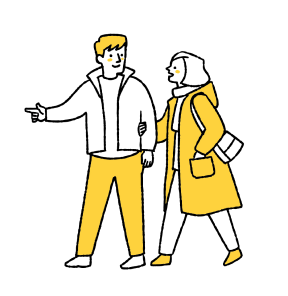秩父市(埼玉県)での お盆 の習慣について、地域ならではの特色を中心にご紹介します。
1. お盆の時期と基本行事
- 秩父地域では、全国一般と同様に 8月13日~16日 にお盆をおこないます(所謂「8月盆」)
2. 家庭での供養と昔ながらの風習
● 盆棚・精霊棚の設置
- 13日の朝に盆棚を設置し、位牌を移して仏壇を掃除し、仏前の扉は開けて供養します。これらは新盆(忌明け後初めてのお盆)にはより丁寧となります。
● お供えと精霊馬
- 季節の野菜・果物・故人の好物・精進料理などを用意し、きゅうりの馬やなすの牛を割り箸等で作って盆棚に飾ります。これは先祖の霊の乗り物とされます。
● 迎え火・送り火
- 13日の夕方には、門や玄関で 迎え火 を焚いて先祖の霊を迎えます。代表的には麻の茎(おがら)を焚いたり、盆ちょうちんを飾る習慣があります。
- 16日の夕方には同じ場所で 送り火 を焚いて霊を再び送り出します。地域によっては霊を迎えて墓地に送りに行く慣習も残っています。
● 墓参り
- 13日頃に家族で お墓参り に行き、墓石を掃除し、ろうそくや迎え火を行って霊を招くのが一般的です。
- もしお墓参りが難しい場合は、自宅の仏壇などに手を合わせることで供養が可能です。
お盆玉(子供へのお年玉に似た慣習)
- 秩父に限った話ではありませんが、全国的には 子供たちに「お盆玉」としてお小遣いや品物を贈る習慣が広まっており、小学生の約37%が受け取っています。現金受け取りが80%、平均9,345円前後という調査結果もあります。
- 特に帰省時などに行われる慣習として、子どもたちに渡されることが多いです。
(秩父市のお盆の流れと特徴)
秩父のお盆の習慣は、全国的な風習と共通する点が多くありますが、地域独自の行事も受け継がれています。
8月13日から16日にかけて、先祖の霊を迎えて供養する「お盆」が行われます。13日には迎え火を焚いて霊を家に迎え、仏壇に盆棚を設けて野菜や果物、故人の好物などをお供えします。きゅうりの馬やなすの牛を飾る精霊馬の風習もあります。期間中には家族で墓参りを行い、16日には送り火を焚いて先祖の霊を見送ります。
また、秩父市上吉田小川地区では、お盆の終わりに「百八灯(ひゃくはっとう)」と呼ばれる火祭りの行事が行われます。通りに並べたかがり火に火を灯し、その煙を浴びることで無病息災を願います。さらに、精霊を送るための神輿も練り歩き、地域の信仰や先祖への敬意を今に伝えています。
このように秩父では、家族や地域のつながりを大切にしながら、伝統的なお盆の行事を丁寧に守っています。
3. 各地の代表的行事・地域的な風習
● 小川地区(秩父市上吉田)の「百八灯と精霊送り」
- 8月16日夜、県道沿いに約400基の篝火(「ウシ」)を並べ火を点けます。
- 点灯後、火がともる通りを三往復しその煙を浴びることで疫病除けとされます。
- 精霊神輿が地区を練り歩き、河原で神輿を置いて先祖の霊を送り出します
● 秩父聖地公園あんどん祭り(秩父市)
- 8月16日、先祖の霊の冥福を祈り灯籠が灯されます。露店・屋台囃子・花火などもあり、地域全体で賑わいを見せます 。
● 船川の千手観音信願相撲(秩父市荒川地区)
- **8月16日**、健康祈願のため奉納される相撲行事で、健康や無事を願う地域固有の慣習です
4. 地域一体となった盆送りと伝統の継承
秩父郡市のお盆は、基本的な仏教儀礼を守りつつ、火を用いた幻想的な盆送り行事や地域行事で特色を持った供養文化が色濃く残っています。