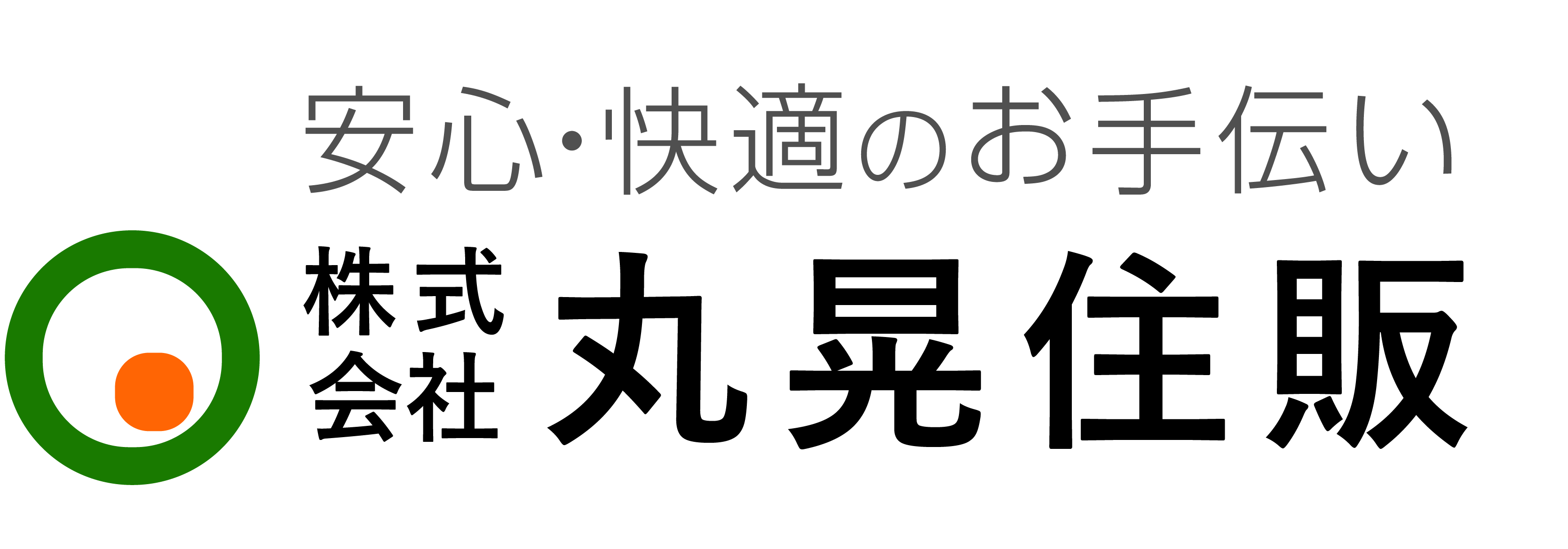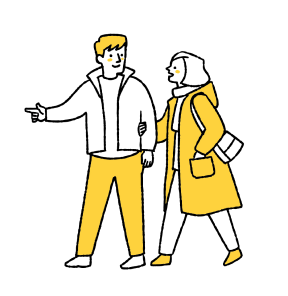大祓の時期
大祓は年に2回行われます。
- 夏越の大祓(なごしのおおはらえ): 6月30日に執り行われます。これは1年の前半の穢れを祓い清め、本格的な夏を前に無病息災を願うものです。
- 師走の大祓(しわすのおおはらえ): 12月31日に執り行われます。これは1年の終わりにこれまでの罪穢れを祓い清め、清々しい気持ちで新年を迎えるための儀式です。
大祓の内容
秩父神社の大祓では、主に以下のことが行われます。
- 形代(かたしろ): 竹と和紙で作られた人形(ひとがた)に息を吹きかけ、自分の罪穢れを移します。この形代は、神事の後にお焚き上げされます。
- 茅の輪くぐり(ちのわくぐり): 茅(ちがや)で作られた大きな輪をくぐることで、身を清めます。作法としては、左回り・右回り・左回りと、数字の「8」の字を書くように3度くぐり抜けます。茅には邪気や毒気を祓う力があるとされています。
- 大祓詞(おおはらえのことば)奏上: 神職と共に「大祓詞」を唱え、心身を清めます。
これらの行事を通して、半年間または一年間の穢れを祓い、心身ともに清らかな状態に戻し、今後の健康と平安を祈願します。どなたでも参加できる神事ですので、秩父神社では当日受付も行っています。
秩父神社の大祓は、古事記や日本書紀にも記述が見られるほど古くから伝わる伝統的な神事であり、日本の文化に深く根ざした重要な行事です。