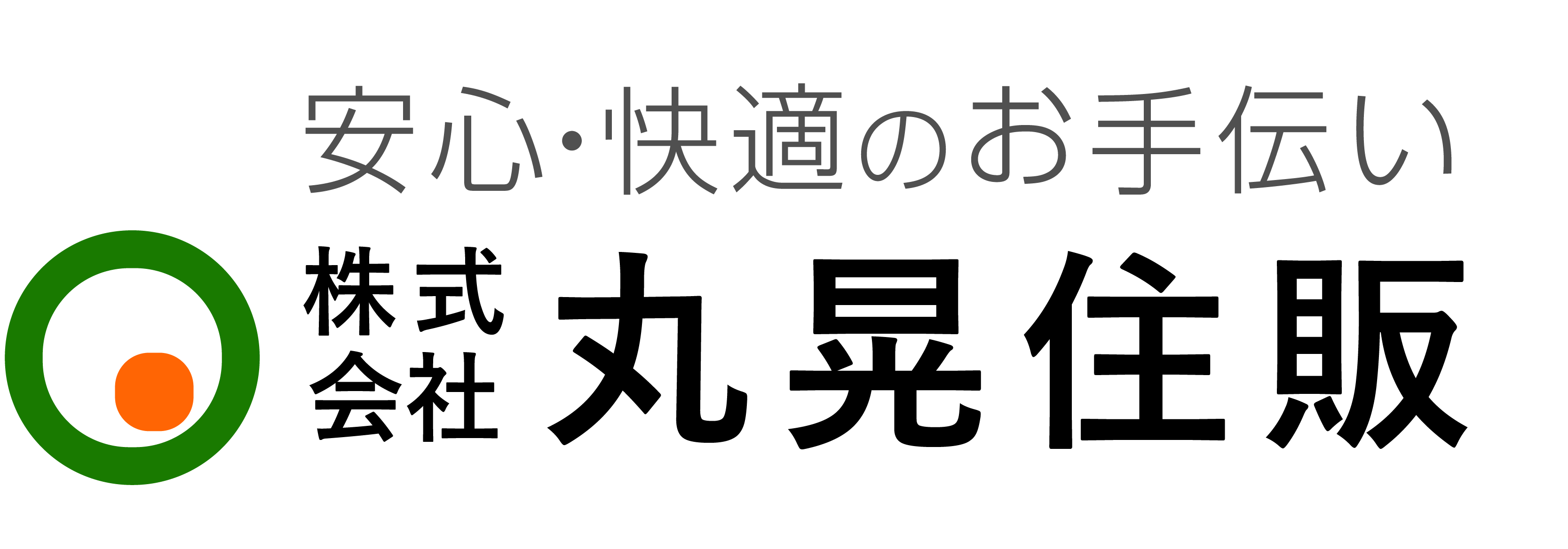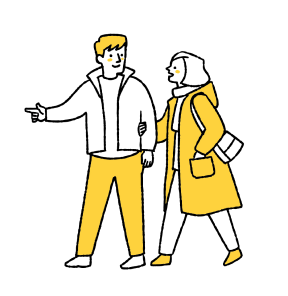秩父地方のお彼岸の習慣には、地域独自の風習や行事がいくつかあります。以下に代表的なものを挙げます。
1. 墓参り
お彼岸の期間(春分・秋分の日を中心とした7日間)には、多くの人が家族で墓参りに行きます。墓石を掃除し、線香や花、供物(果物やおはぎなど)を供えるのが一般的です。
2. おはぎを供える
春は「ぼたもち」、秋は「おはぎ」と呼ばれ、小豆の餡で包んだもち米を先祖の霊に供えます。秩父でもこの習慣は受け継がれており、家庭で手作りすることが多いです。
3. 精進料理を食べる
お彼岸の期間中は、肉や魚を控えた精進料理を食べる家もあります。特に仏教の教えに従う家庭では、この時期に菜食中心の食事を心がけます。
4. 地元のお寺での彼岸法要
秩父市内には多くの古刹や霊場があり、お彼岸の時期になると各地の寺院で「彼岸会(ひがんえ)」が行われます。参詣者は読経を聞き、先祖供養を行います。
5. 秩父札所巡りとの関連
秩父には「秩父三十四所観音霊場」があり、お彼岸の時期に巡礼する人もいます。お彼岸は「彼岸=悟りの世界」に近づく行事とされるため、巡礼もその一環として行われることがあります。